診療案内 - 安城アイクリニック

ららぽーと安城 1F
土日・祝日も診療
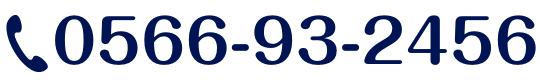

ららぽーと安城 1F
土日・祝日も診療
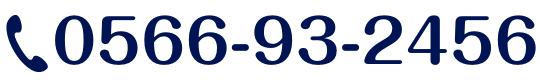

●休診日:金曜日(祝日の場合も休診)
●社保・国保・各種保険取扱い
※受付は診療時間の30分前までとなります。
※初めてのコンタクトレンズ処方の方は診療終了の60分前(午前は12時00分、午後は17時30分)までに受付までお越しください。
視力が落ちた、目がかゆい、痛みやかすみがある、異物感やゴロゴロした感じが続くなど、目に関する違和感や症状はありませんか?
目の不調を引き起こす病気には、非常に多くの種類と原因があります。
また、目の病気の中には、自覚症状がほとんどないまま進行してしまうものも多く、気づいた時には重症化しているケースも少なくありません。
しかし、多くの目の疾患は、早い段階で見つけて治療を始めることで、症状の進行を防いだり、視機能の維持・改善につなげることが可能です。
特に40歳を過ぎた方は、症状がなくても定期的な目の健康チェックを受けることをおすすめしています。目の病気は、早期発見・早期治療が重要です。
大切な目の健康を守るために、ぜひ一度、検査にお越しください。
白内障とは、目の中で“レンズ”の役割を果たしている水晶体(すいしょうたい)が濁ってしまう病気です。
この水晶体が透明であることで、光をスムーズに通して物を見ることができますが、濁ることで光が十分に届かなくなり、視界がぼやけたり、かすんだりします。
白内障は加齢に伴う変化が最も多い原因で、誰にでも起こりうる「老化現象」のひとつです。
そのほか、外傷、糖尿病、薬の副作用(ステロイドなど)、先天性の要因などでも発症することがあります。
以下のような症状が見られる場合は、白内障の可能性があります。
症状はゆっくりと進行することが多いため、気づかないうちに視力に影響を及ぼしていることもあります。
まだ症状が軽い場合は、点眼薬によって進行を緩やかにする治療が行われます。
ただし、点眼薬はあくまでも進行抑制が目的であり、濁った水晶体を元に戻すことはできません。
緑内障とは、視神経(視覚をつかさどる神経)が主に眼圧の上昇などによって障害を受け、それが引き金となって視野が障害(視野角が狭くなる)されている状態です。視野障害の進行具合は非常に緩やかなため、自覚症状が乏しく、病状がある程度進んで視野が狭まることによって気づくケースが多いです。視野障害を一度受けてしまうと、その部分は回復しません。そのため、放置したままにすると失明する可能性があります。緑内障は日本人が中途失明する原因の第1位です。
緑内障は40歳以上の方の20人に1人の割合で発症すると言われています。早期発見・早期治療を可能にするには、40歳を過ぎたらこれといった眼症状がなくとも眼科検診を受けるようおすすめしています。
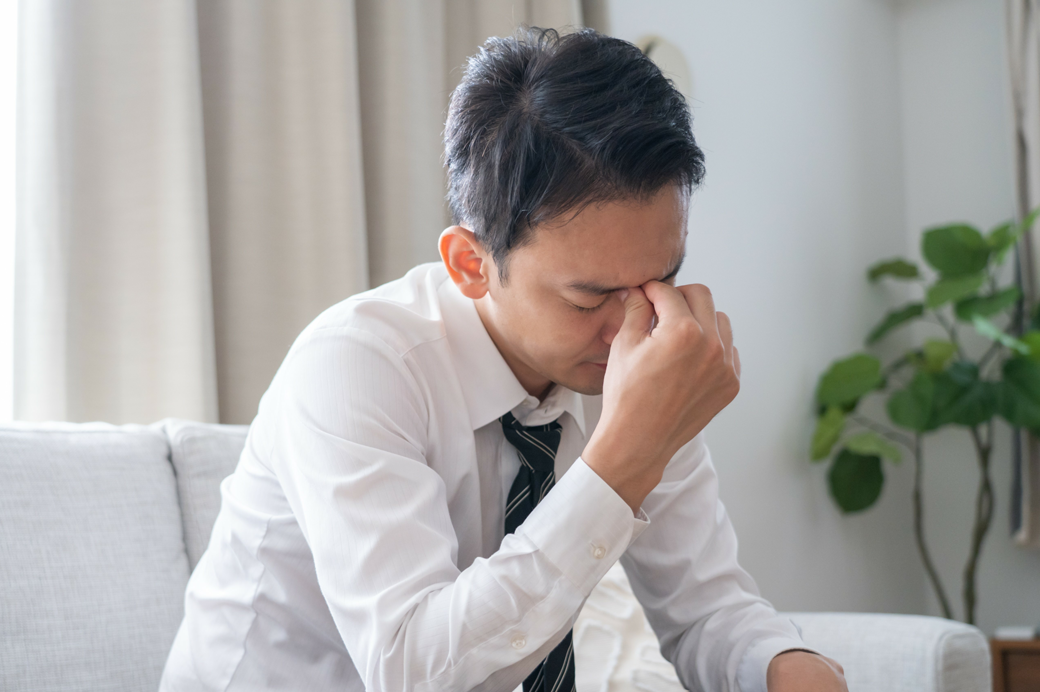
視野の一部に異常が見られますが、範囲が小さかったり、視野の端の方だったりするために、気づかないことも多くあります。
視野の中で見づらい部分も出てきますが、発症していない方の目でカバーしてしまうため、気づかない人もいます。老眼と重なる場合も多く、発見に至らない場合もまだ多い状況です。
視神経の40〜50%に障害が及ぶと、視野の中心部分も見えなくなり、内側(鼻側)から視野が狭くなっていきます。テレビを見ていても見えないところが出てくるなど、日常生活にも支障が出てきます。
緑内障と診断されたら、まず眼圧を下げるための点眼薬による薬物療法となります。
点眼だけでは眼圧が下降しない、症状の進行が抑えられないという場合は、レーザー治療として線維柱体にレーザーを照射して房水を排出させやすくするレーザー線維柱帯形成術や、主に閉塞隅角緑内障に対して行われるレーザー虹彩切開術(虹彩の部分にレーザーを照射してバイパスを作成し、房水を排出させやすくする )などがあります。
また、薬物療法やレーザー治療でも眼圧のコントロールが不十分な場合、手術療法を行います。
アレルギー性結膜炎は、目の表面(結膜)にアレルゲン(アレルギーの原因物質)が触れることで起こる炎症です。アレルゲンとしては、花粉・ハウスダスト(ほこり、ダニ)・動物の毛・カビなどが代表的です。

症状は主に以下のようなものがあります:
症状は両目に出ることが多く、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。
花粉症は季節性のアレルギー性結膜炎の一種で、スギやヒノキなどの花粉が飛ぶ時期に目の症状が強く出るのが特徴です。春だけでなく、秋のブタクサ花粉などでも発症することがあります。
「目がかゆい」「目が腫れる」「涙が止まらない」といった症状がある方は、花粉が原因となっている可能性があります。
アレルギー性結膜炎の治療は、症状を和らげるとともに、アレルゲンとの接触をできるだけ避けることが大切です。
治療としては、点眼薬による薬物療法が基本となります。
症状の程度に応じて、抗アレルギー点眼薬、ステロイド点眼薬、抗ヒスタミン薬の内服などを使用します。
花粉症の季節には早めの対策が重要です。症状が出る前からの予防治療も可能ですので、ぜひご相談ください。
ドライアイとは、目の表面を潤す涙の量や質に異常が生じ、目が乾燥した状態になる病気です。
涙は単に水分だけではなく、目を守り、滑らかに動かすために非常に重要な役割を果たしています。
その涙が不足したり、うまく目の表面にとどまらなくなることで、さまざまな不快な症状が現れます。
パソコンやスマートフォンの長時間使用、空調による乾燥、コンタクトレンズの使用など、原因は様々です。近年は子どもを含めた幅広い層の発症が増えているといわれています。

これらの症状は一時的なものではなく、慢性的に続くことが多いため、放置せず早めの対応が大切です。
ドライアイの治療は、点眼薬で、症状の軽減と涙の安定、目の表面の炎症を抑えることが基本です。
点眼以外の治療としては、涙点プラグ(涙の通り道(涙点)を小さな栓でふさぎ、涙を目にとどめる処置)があります。自然な涙を長くとどめることができ、効果的な治療法のひとつです。
眼精疲労とは、目を使い続けることで疲れや不快感が生じ、休息をとっても十分に回復しない状態をいいます。
単なる「目の疲れ」とは異なり、頭痛や肩こり、吐き気などの全身症状を伴うこともあり、日常生活に影響を及ぼすこともあります。
眼精疲労にはさまざまな要因が関わっており、複数の原因が重なっていることも少なくありません。
デスクワークやスマートフォンの長時間使用や遠視、近視、乱視、老眼などの屈折異常、ドライアイ、ストレスや疲労の蓄積など。
現代では環境の変化から眼精疲労に悩む方が増えています。

眼精疲労の治療は、原因に応じたアプローチが必要です。
原因に対する治療に加えて、ビタミン剤の配合された点眼薬や内服薬、サプリメントなどが有効な場合もあります。
また、生活環境や姿勢の見直し、ストレッチなど身体のケアなどを少し意識するだけで、症状の緩和に繋がる可能性があります。
眼精疲労は、長期間放置すると慢性化し、生活の質(QOL)を下げてしまうこともあります。
気になることがありましたら、小さなサインも見逃さずお早めにご相談ください。
「ものもらい」は、まぶたにできる小さな腫れやできもののことで、医学的には以下の2種に分けられます。
まぶたのふちにある脂や汗の腺に細菌(主に黄色ブドウ球菌)が感染して起こる炎症です。
症状としては:
赤く腫れる、痛みがある、まぶたが重く感じる、膿がたまることもある など。
主に抗菌目薬や軟膏で治療します。膿がたまっている場合は、医師が切開して排膿することもあります。
感染ではなく、まぶたの中にある脂腺が詰まり、炎症を起こしてしこりができる状態です。
症状としては:
痛みは少ない、コリコリしたしこりが触れる、まぶたにふくらみができる など。
自然治癒することもありますが、大きくなった場合は手術で切除することもあります。
飛蚊症(ひぶんしょう)とは、視界にごみや虫のようなものが飛んでいるように見える症状のことをいいます。目を動かしても影は同じ方向に移動しかつ細かく揺れるので、その名のとおり目の前を蚊が飛んでいるように感じます。ただし、影の形はヒモ状やリング状のものなど様々です。普段は気付かなくても、白い壁を見た時や空を見た時に良く見られます。ほとんどの場合は加齢による生理的変化ですが、たまに網膜剥離など重篤な疾患の前触れであることがあるので注意が必要です。
飛蚊症の原因にはいくつかあり、大きく分けて「生理的なもの(加齢など)」と「病的なもの(治療が必要な病気によるもの)」の2つに分類されます。
これは病気ではなく、自然な変化によって起こる飛蚊症で、多くの人が該当します。
放置すると失明のリスクもあるため、早期の診断・治療が重要です。
飛蚊症のほとんどは、加齢による自然な現象であり、特別な治療を必要としないことが多いです。
しかし、中には治療を要する深刻な目の病気のサインである可能性もあるため、飛蚊症に気づいた場合は、念のために一度、眼科で眼底の検査を受けることをおすすめします。
糖尿病網膜症は、糖尿病腎症や糖尿病神経障害と並ぶ、「糖尿病の三大合併症」のひとつです。日本では、成人の失明原因の第3位にあたります。
糖尿病は、血糖値(血液中のブドウ糖の量)が高い状態が続くことで、全身の血管や神経に障害を与える病気です。その影響は目や腎臓だけでなく、脳や心臓など全身に及び、最悪の場合、命に関わることもあります。
糖尿病が「恐ろしい病気」とされるのは、こうしたさまざまな合併症を引き起こす可能性があるからです。
中でも、糖尿病網膜症は、目の奥にある網膜の細い血管が徐々に詰まっていく病気です。進行すると、眼の中で大きな出血が起きたり、異常な血管や膜が形成されて網膜が引っ張られて剥がれてしまう(網膜剥離)、視神経がダメージを受けるなどして、最終的に失明する可能性もあります。
この病気は初期段階ではほとんど自覚症状がありません。そのため、気づかないうちに進行してしまうケースが多くあります。
したがって、糖尿病と診断されたら、定期的に眼科を受診し、必要なタイミングで治療を受けることが非常に重要です。
糖尿病網膜症は、進行の段階に応じて次の3つのタイプに分けられます
糖尿病では、血液中の糖が血管に悪影響を与え、血管は詰まりやすくなったり、もろくなって破れやすくなります。
中でも、網膜の毛細血管は体の中でも特に細かいため、糖尿病による影響がいち早く現れやすい部位です。
網膜には、視力を保つために酸素を届ける毛細血管が張り巡らされていますが、糖尿病によって血流が悪くなると、網膜は慢性的な酸素不足に陥ります。
その結果、体は酸素を補おうとして、新たな血管(新生血管)を作ろうと反応します。
ところが、こうしてできた新生血管は構造的に未熟で、非常に破れやすく、簡単に出血してしまうという特徴があります。
この出血が視界のかすみや視力低下といった症状を引き起こす原因になります。
また、若い人ほど新陳代謝が活発であるため、網膜症の進行が早くなる傾向があり、より一層の注意が必要です。
単純網膜症の段階で視力がまだ良好である場合には、食事や運動、薬の力を借りて血糖値をうまく管理することで、症状の進行を防ぐことが可能です。
血糖値が安定していれば、小さな出血などは時間の経過とともに自然に吸収され、改善することもあります。
なお、ほかの治療を受ける際も、血糖値のコントロールは引き続き重要で、常に続けていく必要があります。
視力の低下が見られる場合や、病気が前増殖型網膜症の段階に進行した場合には、**レーザーを使って網膜の特定部位を焼き固める「光凝固治療」**が行われます。
特に、視力に直結する重要な部分である黄斑部にむくみ(浮腫)が出た場合は、レーザーを照射してその腫れを抑えることで、視力の低下を防ぐ効果が期待されます。
もし黄斑部に浮腫が生じて視力が低下した場合には、抗VEGF薬(VEGF=血管内皮増殖因子:新しい血管を作り出す因子)を目の中(硝子体)に直接注射する治療が行われます。
この注射により、異常な血管の増殖や漏れを抑え、浮腫を軽減して視力の回復が期待できます。
症状が進行してしまった場合には、手術が必要になります。
出血の除去、網膜剥離の消失、網膜症の沈静化、黄斑浮腫の改善などにより視機能の回復が期待できます。
黄斑変性とは、網膜の中心部に位置する黄斑に異常が起きることで、視力に障害を引き起こす病気です。
特に加齢黄斑変性は、欧米では成人の失明原因の第1位を占めており、日本でも高齢化の進行や生活習慣の欧米化に伴って患者数が急増しています。この病気は50歳以上の約1%に見られ、年齢とともに発症率が高くなります。
加齢黄斑変性は、年齢を重ねることで網膜色素上皮の下に老廃物が蓄積し、それが直接的または間接的に黄斑部の機能に影響を与えることによって発症します。
この疾患には大きく分けて2つのタイプがあります。
この異常な血管は正常な血管とは異なり、血液の成分が漏れ出したり、破れて出血したりする特徴があります。
血液の成分が漏れ出すことで網膜にむくみ(網膜浮腫)が生じたり、液体が網膜下にたまる(網膜下液)といった変化が起こり、網膜の正常な機能が損なわれて視力が落ちていきます。
さらに、血管の破れによる出血が網膜にダメージを与える場合もあります。
網膜の腫れや網膜の下に液体が溜まると網膜がゆがみます。
ゆがんだフィルムで写すとゆがんで写るように、ゆがんだ網膜で見るとものがゆがんで見えます。
黄斑部は障害されますが周辺部は障害されていませんので、中心部はゆがんで見えますが周辺部は正しく見えます。
さらに黄斑部の網膜が障害されると、真ん中が見えなくなり(中心暗点)視力が低下します。
視力低下が進行すると、運転免許の更新や字を読んだりすることができなくなります。
通常、視力低下は徐々に進行し、治療をしなければ多くの患者さんで視力が0.1以下になります。
網膜下に大きな出血が起こると突然、著しい視力低下が起こることがあります。
症状が進行すると色が判別できなくなってきます。
加齢黄斑変性の治療には、抗VEGF薬の注射、レーザー治療、光線力学的療法(PDT)、硝子体手術などがあります。
治療は症状の進行を抑えることを目的としています。
また、サプリメントの摂取や生活習慣の見直し、適度な運動なども病状の進行を抑えたり、予防につながる可能性があり有効です。
定期的な経過観察を行い、目の状態を把握することが重要です。
眼の健康は、学習や日常生活に大きく関わる大切な要素です。特に成長期のお子さまは視力が変化しやすく、近視や乱視などが進行していることに気づかない場合も少なくありません。
学校健診では視力のスクリーニングが中心となりますが、視力低下の原因や詳しい目の状態までは判断できないため、検査結果で指摘を受けた場合は、ぜひお早めに専門医の診察を受けてください。
保護者の皆さまにも安心してご来院いただけるよう、検査結果や治療方針についても丁寧にご説明いたします。お子さまの目の健康を守るために、気になることがあればいつでもご相談ください。

会社で行われる健康診断で、要再検査や指摘を受けた場合は、早めに眼科を受診し、より詳しい検査を受けることをお勧めします。
目の病気は自分では気づかないうちに進行していることがあります。早期発見、早期治療が重要です。
例えば緑内障は「気づかないうちに視野が狭くなっていく病気」と呼ばれ、進行するまで日常生活に支障が出にくいため、発見が遅れることがよくあります。
当院ではより精密な検査にも対応可能です。
病気の有無や進行度、今後の治療方針についてわかりやすくご説明いたします。
40歳以上の方、数年間眼科を受診していない方、症状はないが目の健康を確認したい方なども定期的な受診をおすすめいたします。
当院では、患者様お一人おひとりのライフスタイルや視力の状態に応じて、最適な眼鏡やコンタクトレンズをご提案・処方しております。
特にコンタクトレンズは、目に直接触れる医療機器であり、誤った使い方をすると感染症を引き起こしたり、重度の視力障害に至る恐れもあります。
そのため、当院ではコンタクトレンズを安全にご使用いただけるよう、装用の練習や日常のケア方法について、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
安心して快適な視生活を送っていただけるよう、しっかりとお手伝いさせていただきます。

初めてのコンタクト処方の方は
60分前(午前は12時00分、午後は17時30分)までに受付にお越しください。
装用練習にお時間がかかります。お時間に余裕をもってご来院ください。
また、ご使用中の眼鏡をお持ちの方は、ご持参ください。
